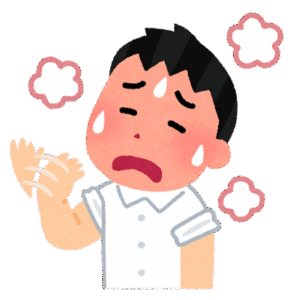今回はちょっとモヤモヤしていることを書いてみます。
内容ですが、それが悪いとかではなくてそういう考え方もあるんだなぁ…と私は思うようにしています。
いまから遡ること約一年前のこと、ある展示会終了後のアンケートで展示会(ブース)に学生がくることについて問いがありました。
私はそれを見た時に即答で『MATSUMURAは、ありです!』と答えたのを覚えています。
なぜなら、MATSUMURAの展示会へ出展する目的は『新規顧客獲得』や『協力メーカーの開拓』もありますが、もうひとつ『学生へモノづくりの愉しさを伝えたい』があるからです。7月からスタートした私のラジオ放送もそういった想いがあるから、それを選択し進めてきました。
話戻りますが、学生にブースに来てほしくないなんて選択は私には無いんです。
MATSUMURAのブースへ立ち寄ってもらい、モノづくりの愉しさや、世の中を支えている職人の想いや製品を見てもらい、少しでもモノづくりに興味を持っていただければ、学生さんが就職を考えた時に製造業も選択肢として入ってくればいいじゃないですか
今もですが、これから先人手不足はもっと深刻になってきます。
製造業は下に見られがちなところもあり、もっとモノづくりの愉しさを伝えていかなければならない時に、学生は来ないでくださいを掲げてどうするの?と思ってしまいます。
私が学生の立場ならそういうことを掲げている企業へは良い印象を持たないと思います。
人によってはSNS等でもつぶやかれたりするかもしれませんね。
毎年伺っている『かさがけ商工フェア』なんかは規模こそそんなでもないですが、積極的に地域の学生に見学してもらい、学生も企業の生の声を聴ける大変すばらしい展示会です。
バスで展示会へ来てくれる学校も増えてきて、私の個人的な思いは『ありがたい』しかありません。
企業ごとに考え方もカタチも色も違いますのでしょうがないとは思いますが、見てるPOINTがずれてしまうと、後々痛い目を見るのは間違いないです。
ひと昔前の当たり前は今は通用しませんし、逆な効果が出ることもあるので、トップはよく観て(観察の観る)変化に柔軟に対応していくことと、挑戦が大事だと考えます。
『ノー残業デー』なんか一昔前は『ホワイト企業だね』なんて思われていたかもですが、私からすれば『うちはブラックです』と胸張って世間に言ってるのと同じだと思ってます。
そんなことを思った今日この頃です。
最後に私が若いころから大切にしている言葉を付け加えて締めたいと思います。
何をするにもこれは大切なことだと思っています。MATSUMURAのSNSでも活かされている内容です。
※原文はちょっと難しいので、AIに要約してもらったものを載せますね。
二宮尊徳『湯船の教え』
1. 湯をかき寄せる、押し出す例え
この教えは、**「奪うに益なく譲るに益あり」**という天理(自然の道理)を説明しています。
- **湯を自分のほうに掻き寄せると、**一時的には自分のほうに来るように見えても、結局は脇から向こうの方へ流れていってしまいます。これは、自分の利益ばかりを追求したり、奪い取ろうとしたりする行為を表します。一時的な利得はあるように見えても、結局は続かず、全体としては何も得られない、むしろ失うことになると説いています。
- **湯を向こうの方へ押してみると、**向こうへ行くように見えても、やはりこちらの方へ流れて戻ってきます。少し押せば少し戻り、強く押せば強く戻る。これは、他者のために尽くしたり、与えたりする行為を表します。一見すると自分のものが減るように思えても、巡り巡って自分に返ってくる、つまり、与えることが結果的に自分の豊かさにつながるということを示しています。
この教えは、「仁(思いやり)や義(正しい行い)とは、湯を向こうへ押す(他者に与える)時の名前であり、手前に掻き寄せれば不仁・不義となる」と、利己的な行為への戒めを含んでいます。
2. 湯船に立って湯の浅さを嘆く例え
この教えは、**「分度(身の丈を知る)の大切さ」**を説いています。
- 豊かな人が湯船の中に突っ立って、かがみもせずに「湯が浅い、膝までもこない」と不平を言うのは、自分の「分限(身の丈や限度)」を知らずに、いくら財産があっても満足せず、さらに多くを欲しがる姿に例えられています。
- 尊徳は、「自分がかがみさえすれば、湯はたちまち肩まで来て、自然と十分になるだろう」と述べ、自分の立場や状況を正しく認識し、その範囲内で満足すること(分度を守ること)の重要性を説いています。分度を守れば、余財(余った財産)が自然とでき、それを他者に譲ることで、世の中全体が豊かになり平和になると考えました。
現代における湯船の教えの意義
二宮尊徳の湯船の教えは、現代社会においても非常に重要な示唆を与えています。
- **「奪うに益なく譲るに益あり」**は、短期的な利益追求ではなく、長期的な視点での共存共栄の精神に通じます。ビジネスにおいては、顧客や社会への貢献が結果的に自社の成長につながるという考え方や、SDGsのような持続可能な社会を目指す動きとも関連します。
- **「分度」**は、際限のない消費や欲望を戒め、自己の現状を認識し、足るを知ることで精神的な豊かさや安定を得ることの重要性を示しています。これは、ミニマリズムやシンプルな暮らしといった現代の価値観とも共鳴します。
湯船の教えは、単なる経済的な教えに留まらず、人間関係、社会貢献、心の持ち方など、人生全般にわたる普遍的な真理を示していると言えるでしょう。